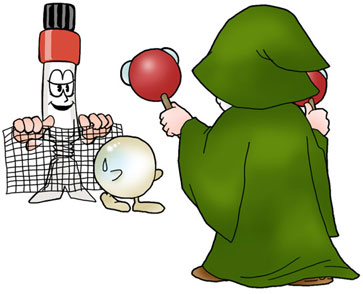|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
Location:Home > テクニカル情報配信サービス > バイオダイレクトメール > 生化夜話 |
||
生化夜話 第36回:界面活性剤が教えてくれたクロマトグラフィー - 疎水性相互作用クロマトグラフィー
無極性分子や大きな無極性領域をもつ極性分子は水溶液中で凝集する性質があります。水にはじかれた分子はそういった分子同士で集まった方が熱力学的に安定します。これを教科書的には疎水性相互作用、疎水効果などと呼びます。 細胞膜を構成する脂質二重層、タンパク質の立体構造など生物のさまざまな場所で作用している力ですが、これが生体分子の精製に活用されるまでには少々時間が必要でした。 溶質と担体の相互作用クロマトグラフィー実験における疎水性相互作用は、当初は特定の条件下で生じる溶質と担体の相互作用として観察されてはいたようです。 非常に古いところでは、1948年にティセリウスが報告した塩析の研究に記述があり、塩が存在しない溶液中ではタンパク質に対してアフィニティーを示さない、もしくはごくわずかのアフィニティーしか示さない吸着材が、高塩濃度ではよい吸着材になることがあると書いています。 その14年後、ティセリウスの教え子の一人であり、ゲルろ過で有名なポラートが、ヒト血清タンパク質の分離を行いました。この実験では、Sephadex™ G-100のカラム中に硫酸アンモニウムのグラジエントを形成し、溶解度の違いで沈殿する位置が変わることを利用して分離しました。 塩濃度を上げることで静電相互作用が抑えられ、タンパク質の疎水的な領域と吸着材との相互作用の影響が現れたものと思われます。ただ、これらの研究ではっきり疎水性相互作用を意識していたかというと、疑問です。 部分的にでも意図して疎水性相互作用を生体分子の分離に使った最初の例は、1967年、カナダ医学研究局のイアン・ジラムによるtRNAの精製のようです。ベンゾイル化DEAEセルロースを吸着材として、DEAEの静電相互作用と、ベンゾイル基の疎水性相互作用の両方での精製を狙いました。ただ、イオン強度を上げることで溶出できていることからすると、静電相互作用が主で、疎水性相互作用の寄与は限定的だったのでしょう。 1970年にはミュンヘン大学のヴァイスとブッヒャーが、疎水性相互作用をミトコンドリア膜タンパク質の精製に用いました。 このように、溶質と担体の疎水性相互作用が観察された事例や、それを生体分子の分離に応用した事例もあるにはあったのですが、積極的に用いられる手法ではありませんでした。 科学と技術と1970年代に入って、科学的知見と技術の両方から状況が変わりはじめました。 初期のX線構造解析で得られた結果では、疎水性アミノ酸はほぼタンパク質の内部に分布していました。しかし、1970年代に入って事例が増えてくると、疎水性アミノ酸がしばしばタンパク質の表面に露出していることが明らかになりました。この科学的知見から、タンパク質の精製に疎水性相互作用を利用できる見込みが高まりました。 技術的側面で重要な契機となったのは、CNBrを用いた化合物とアガロース担体のカップリング法でした。アクセンとポラートが開発したこの技術は、1967年に発表されたアフィニティークロマトグラフィーの基盤となりましたが、疎水性相互作用クロマトグラフィーの実用化においても重要な役割を果たしました。 CNBr法で疎水性クロマトグラフィー担体をつくった最初の例は、チェルシーカレッジのヨンの実験のようです。ヨンは疎水性アフィニティークロマトグラフィーと称して、アミノデシル化したSepharose™ 6Bで親油性タンパク質を精製しました。ただ、ヨンの担体は疎水性相互作用とイオン性の相互作用の両方を示すものだったので、タンパク質を変性させてしまうような厳しい条件でないと溶出できない場合があるという問題がありました。 こうした着想の元になったのは、ヨンが後に書いているところによれば、アフィニティークロマトグラフィーの論文で、クアトレカサスがスペーサーとして使っていた疎水性のポリメチレン鎖が、タンパク質の吸着サイトになった現象のようです。 この最初の事例が出てきた翌年の1973年、CNBr法の本家であるウプサラ大学のポラートも、疎水性相互作用クロマトグラフィーの研究成果を報告しました。 それまでの電荷をもつ両親媒性担体では、疎水性相互作用だけでなく電荷による静電相互作用もはたらくため原理が複雑になり、結果の解釈に苦労することもありました。それなら静電相互作用を抑えよう、とすれば、3.3M NaClのような高い塩濃度が必要になってしまいます。そこで、ポラートは新しいタイプの疎水性相互作用クロマトグラフィー担体として、電気的に中性な両親媒性担体を開発しました。この時ポラートが開発したベンジル化Sepharose™ 6Bは、結合容量が大きく、高い分離能を手軽に実現できました。しかし、ポラートの論文は、こうすればできる、という手法の報告であって、どうして疎水性相互作用クロマトグラフィーができるのか、という物理化学的な原理については、よくわからないがタンパク質の周りの水分子の変化ではないかと推測するに留めています。 界面活性剤の功績ポラートの他にも、ウプサラ大学には疎水性相互作用クロマトグラフィーの基盤となった技術の生みの親がいます。大量かつ高純度のアガロースを調製する方法を考案したヤティーンです。彼もポラートに続いて1974年に疎水性相互作用クロマトグラフィーの論文を発表しています。ヤティーンは他の研究者と違い、彼自身の研究から疎水性相互作用クロマトグラフィーの着想を得ました。 膜タンパク質の可溶化には界面活性剤を使います。膜タンパク質の疎水性の部分と界面活性剤分子の疎水性の部分が相互作用しているのですが、それならば界面活性剤の分子を担体に固定化すればタンパク質をトラップできるのではないか、と考えたのだそうです。 そこでDEAE-Sephadex™にSDSを静電的に結合させた担体や、アルキルアミンをCNBr法でSepharose™にカップリングした担体をつくってみました。これでタンパク質を結合させることはできたのですが、疎水性相互作用以外の原理もはたらくためデータが複雑で、さらに結合したまま離れないタンパク質もありました。 それからの数年、ポラートのグループとヤティーンのグループは、疎水性相互作用クロマトグラフィーについて多数の研究を行い、疎水性クロマトグラフィーに適した担体の合成から、その一般的な特性まで調べ上げ、今日も使われている疎水性相互作用クロマトグラフィーの基礎を固めました。 これの名はさて、ここで終わってしまっては、生化学に関する余談のネタたる生化夜話として、鼎の軽重を問われかねませんので、ここで一つ無駄話を。 本稿ではヤティーンの命名による疎水性相互作用クロマトグラフィー(Hydrophobic Interaction Chromatography、HIC)で通してきましたが、この手法についてはさまざまな呼び名が提唱されていて、(筆者が調べた範囲ではHICが今日では多数派のように見えますが)研究者の間で名称についてのコンセンサスはないようです。 疎水性相互作用クロマトグラフィー以外に、Hydrophobic bonding、Hydrophobic chromatography、Hydrophobic affinity chromatography、Salting-out adsorption chromatographyなど、いろいろありました。その中でも極めつけはポラートの初期の論文に出てきた名前でしょうか。 A method for protein fractionation based on hydrophobic salting out adsorption in non-ionic amphiphilic gelsという長いもので、日本語にすると「非イオン性両親媒性ゲルを用いた疎水性塩析吸着によるタンパク質分画法」といったところでしょうか。 参考文献
お問合せフォーム※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。 お問い合わせありがとうございます。 |
||
© 2026 Cytiva