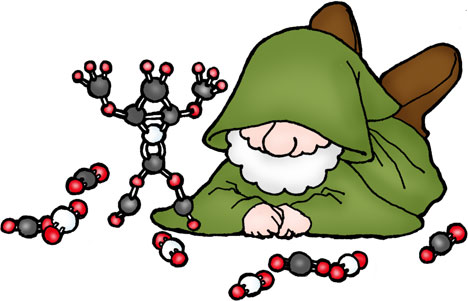|
||
|---|---|---|
|
|
||
|
Location:Home > テクニカル情報配信サービス > バイオダイレクトメール > 生化夜話 |
||
生化夜話 第5回:数秒じゃなくて5000年でした現在では蛍光や発光などさまざまな手法を使って、生体分子の動きを追跡することができますが、かつては生体分子の追跡といえば放射性同位体(ラジオアイソトープ、RI)を使うのが普通でした。 天然モノの時代レントゲンによるX線の研究が1895年、キュリー夫妻によるラジウム・ポロニウムの発見が1898年、ラザフォードがα線の散乱から原子核を発見し原子模型を発表したのが1911年等々と、19世紀末から20世紀はじめにかけて放射化学や核物理に関する基礎的な発見がなされています。実は、放射性同位体を分子を追跡するための目印(トレーサー)として使うというアイディアは、放射性同位体の研究がようやく始まったかどうかというこの時期にまで溯れるのです。 時は1911年、場所はイギリスのマンチェスター、前述の原子模型を発表したラザフォードのラボの地下室です。その当時、オーストリア政府がラジウムなど各種放射性物質をラザフォードに提供していました。その中には、ラジウムが含まれていると思われる放射性の鉛が大量にありました。ラボの地下室にはその鉛が保管されていました。 大量の鉛を前に、ラザフォードが非常に砕けた口調で、ラボの若手ヘヴェシーをけしかけました。その言葉は、1944年のヘヴェシーによるノーベル賞受賞講演によると「My boy if you are worth your salt, you try to separate radium D from all that lead」だそうです。意訳してしまえば「おい若ぇの、俸給分の仕事ができると言うんなら、この鉛の山からラジウムDを取ってみろや」といったところでしょうか。ヘヴェシーは1912年まで大変熱心にその仕事に取り組みました。しかし、ラジウムDとは現在の名称では210Pbと表記される鉛の放射性同位体であり、化学的性質の変わらない大量の鉛の中から、微量にしか含まれていない放射性同位体を当時の技術で取り出すのは、容易な仕事であるとはとても思えません。案の定、ヘヴェシーの努力は何の成果もなく終わります。 この研究は失敗と片付けてしまっていたらそれまでですが、ヘヴェシーはあまりにも「ガッカリ」なこの結果を一捻りし、「どう工夫しても鉛から分離できなかった」ことを利用してみることにしました。その当時、ラジウムを大量に保有していたウィーン研究所に移ったヘヴェシーは、共同研究者のパネートとともに、ラジウムD(210Pb)を使ってクロム酸鉛等の化合物の溶解性を調べる実験を行い、1913年にその結果を報告しました。この研究が放射性同位体をトレーサーとして用いた世界最初の例になりました。 人工モノの時代放射性同位体をトレーサーとして使い始めた頃は、当然、天然の放射性同位体を使うしかありませんでした。しかし、前述の鉛のように、生体分子の構成要素としてあまり使われていない元素では、できる研究も限られています。炭素や水素など、生体分子に多く含まれている元素の同位体であれば研究の幅が広がります。また、実験のたびに天然の原料から分離していたのでは準備が大変ですし、そもそも研究に適した同位体が存在するかどうかという問題もありますので、人工的に作り出せれば、さらに好都合です。 そんな応用研究側の事情を知っていたかどうかはわかりませんが、人工的に放射性同位体を作り出す技術が開発されました。1934年にフレデリック・ジョリオ・キュリー、イレーヌ・ジョリオ・キュリー夫妻がホウ素、アルミニウム、マグネシウムにα粒子を照射して、13N、30P、27Si、28Alを生成することに成功しました。また、フェルミは自然に存在する元素に中性子を照射して多数の人工放射性同位体を生成しました。 時期が前後しますが、この時期の重要なできごととして、元素に粒子を照射するために使う加速器の整備が進んできたことが挙げられます。1929年、ローレンスが、世界で最初のサイクロトロンをバークレーに建設しました。サイクロトロンはそれまで使われていた加速器よりも高いエネルギーの粒子を作り出すことができました。 こうして舞台が整ってきた1935年に、人工放射性同位体を使った最初のライフサイエンスの実験が行われました。ヘヴェシーは、32Pが入った餌をラットに与え、32Pがどこに貯まるのか、そしてそれが時間の経過によってどう変化してゆくのかを調べました。 1930年代末になると、放射性同位体は生化学の分析に頻繁に使われるようになりました。例えば、シェーンハイマーは、窒素の同位体を使ってラットのタンパク質のロイシン含量を調べる研究などを行いました。ちなみに、その当時は脂肪やタンパク質のような生体分子は安定で、組織が置き換わる場合を除けば変化しない分子であると思われていました。しかし、シェーンハイマーの一連の研究により、生体分子は、食物から取り込まれた分子を使って、日々新たに作り直されている実は非常にダイナミックな分子であることが明らかになりました。 炭素の放射性同位体
生化学・有機化学では炭素(C)が重要です。今日、研究に使われる炭素の同位体の代表といえば14Cです。14Cは半減期が5730年と長いため、生化学や医学などさまざまな分野で重宝されることになりますが、実際には最初に使われたのは半減期が短い11Cで、1939年にルーベンとケイマンが方法を考案しました。 20分の勝負、11Cルーベンとケイマンの業績があっても、「こうして炭素の放射性同位体を使えるようになったことで研究の幅が広くなり、生化学の解析は一気に進んだのでした、メデタシメデタシ」とはいきませんでした。確かに、炭素の放射性同位体が使えるようになったこと自体は歓迎すべきことなのですが、11Cの半減期は20分強と短かったのです。さらに困ったことに、使用前に超遠心で調製しなければならないのですが、11Cの調製に使える超遠心装置がサイクロトロンが設置されていたバークレーにはなく、当初は車で50分かかるスタンフォードに行くしかありませんでした。バークレーとスタンフォードの間の道路は渋滞がひどかったらしく、何とか早く行けるように警察に先導を頼んだこともあったそうです。後に、バークレーから10分ほどで行けるシェル石油のラボの超遠心装置が使えるようになりましたが、そもそも超遠心自体もある程度時間のかかる作業ですので、抜本的な解決にはなりません。そんな作業に疲れてしまったルーベンとケイマンは、もっと半減期が長い炭素の同位体ができなかったら、もう炭素の同位体を使った研究は止めようと考え始めました。 せいぜい数秒?14C14Cの存在を最初に予言したのはイェール大学のカーリーでした。その後、ケイマンを含む何人かの物理学者の研究により、14Cの存在はほぼ確実視されるようになり、実は前述の11Cの使用法を考案するよりも前の1937年には物理学的には14Cが生成されたことが確認されましたが、その性質はわかっていませんでした。この時点では、14Cは放射性の同位体であり、β崩壊して14Nに変化すると予測されていました。また、余分な中性子を2つもつほかの同位体は半減期が非常に短いものが多いことから、14Cの半減期も短く、せいぜい数秒ではないかと考えられていました。 そのような予測に基づき、14Cの生成と非常に半減期の短い放射性同位体を検出するための実験が何度も行われました。しかし、その当時14Cの生成に使われていた内部標的法では得られる量があまりにも少なかったことと、そもそも実験系の前提が間違っていたことから、14Cの性質をはっきりさせることはできませんでした。 14Cの研究に悪戦苦闘したり、半減期の短い11Cを乗せて車を走らせたりしている間に、ケイマンにある機会が訪れます。サイクロトロンの責任者であるローレンスが、その時バークレーにあった2台のサイクロトロンをフルに使ってよいと言い出しました。ローレンスは新しいサイクロトロンの建設費を生物学関係の予算から獲得しようとしていたのですが、そのためには、炭素、窒素、酸素のいずれかの半減期の長い同位体を生成し、サイクロトロンが生物学の研究に役立つことを示さなければならないからでした。 ケイマンはローレンスの求めに応じて生物学研究に使える元素の同位体を徹底的に試してゆき、その中には当然14Cも含まれていました。そして1940年2月、ついに14Cの生成に成功し、調べた結果、放射性の同位体ではあるものの、半減期は当初の予測とは異なり非常に長いことがわかりました。 こうして見事に生物学研究に使える画期的な放射性同位体を生成することに成功したケイマンですが、サイクロトロンでの作業が多すぎたため、すっかり放射線コンタミ人間になってしまいました。アベルソンとの共同研究ではバックグラウンドの異常な変動に悩まされ、最終的にケイマンと検出器の距離の変化に応じてノイズが変化することが判明しました。また、ルーベンとの研究では、アッセイ担当のルーベンの仕事中は、常に検出器から離れていることになりました。(いかにも健康に悪そうな話ですが、ケイマンは長生きし2002年に89歳で他界しました。) その後の14C第二次世界大戦が終わり、原子物理学の平和利用が盛んになるのに合わせて、研究用の14Cも十分に得られるようになりました。その14Cを使って、14Cのトレーサーで複雑な反応を解明した最初の例となる、生化学史上重要な研究が行われました。 カルビン回路光合成そのものはかなり古くから知られている現象で、19世紀中には「CO2+水→植物の成長+O2」という考えが確立していました。しかし、1938年までは、何が入って何が出てくるのか、の研究に終始しており植物の中で行われている反応そのものは、研究する手段がないため謎のままでした。その謎の部分に、14Cとワットマンろ紙を組合わせたラジオクロマトグラフィーで挑んだのがカルビンたちでした。 彼らは、14Cで標識した重炭酸塩を含む培地でクロレラを培養し、短時間光をあててからクロレラを熱アルコール処理、糖化合物を抽出してペーパークロマトグラフィーで分離するという実験を繰り返し、今日カルビン回路として知られている非常に複雑な経路を明らかにしました。 14Cの製造いくら14Cが便利だといっても、サイクロトロンはどこにでもあるものではありませんし、研究者が毎回自作しているようでは研究が進みません。14Cの普及には、専門の企業による製造が欠かせませんでした。14Cを製造する企業は何社もありますが、その中でも最も古いものの1つが第二次世界大戦中のイギリスで誕生しました。 第二次世界大戦中、イギリス政府は、ポルトガルからドイツ向けに出荷された大量のラジウムを押収しました。このラジウムは機械のダイヤルや軍用機の照準器に使用する発光塗料の材料でした。イギリスでは、1940年から若い有機化学者グローブのチームがバッキンガムシャーのアマシャムで活動を開始し、同様の目的でラジウムの精製を行いました。当初の精製量は微々たるものでイギリス政府を心配させましたが、1944年までに発光塗料500 kgの製造に十分な量のラジウムを製造しました。 1946年、グローブのチームにある転機が訪れます。イギリス政府は天然同位体の精製と人工同位体の生成を行うナショナルセンターを設立し、科学、医学、産業界が必要とする放射性同位体を供給することを決定しました。バッキンガムシャーの施設とグローブのチームがそのセンターとなり、1949年には14Cを使った最初の化合物である酢酸ナトリウムを出荷しました。同年、The Radiochemical Centreと改称した彼らは、1950年代には14Cの化合物だけで200以上をラインアップするまでに成長し、後にアメリカと日本に現地法人を設立しました。 参考文献
お問合せフォーム※日本ポールの他事業部取扱い製品(例: 食品・飲料、半導体、化学/石油/ガス )はこちらより各事業部へお問い合わせください。 お問い合わせありがとうございます。 |
||
© 2026 Cytiva